
子育て・仕事・家事に毎日追われる中で、「家計管理しないと…でも時間がない!」と思っているママ、多いのではないでしょうか?
私もそのひとりです。でも、家計簿アプリとの出会いで家計の把握がグンとラクに!
今回は、私が実際に使っている「マネーフォワード for ひまわり生命」アプリを中心に、家計簿を楽しく続けるコツをご紹介します。
家計簿アプリって本当に便利?私が選んだ理由
家計簿アプリはたくさんある中で、なぜ「マネーフォワード for ひまわり生命」を選んだのか。
それは「手間をかけずに、自動で家計が見える」からでした。
このアプリは、「マネーフォワードME」と同じ機能をベースにした無料の家計簿アプリで、誰でも利用可能です。
銀行口座やクレジットカード、電子マネーなどと連携すれば、自動で出入金を記録してくれるので、本当にラク!
アプリの基本機能と使い方
スマホひとつでできる!主な機能
- 銀行口座・カードとの連携
- 支出の自動分類(食費・日用品・教育費など)
- カレンダー形式で収支チェック
- 月ごとの予算設定と残高管理
- レポート機能で収支の傾向がわかる
特に便利なのが、無料版でも最大10件まで金融機関と連携できるという点。
複数口座をお持ちの家庭や、家族のカードもまとめて管理したい場合にとても重宝します。
最初に使うときは、アプリをインストールして金融機関との連携設定をするだけ。
あとは毎日スマホを開くだけで、「今日は使いすぎたな」「今月は教育費が多めかも」など、感覚ではなく数字で家計を把握できます。
「マネーフォワード ME」との違いは?
「マネーフォワード for ひまわり生命」は、マネーフォワード ME(エムイー)とほぼ同じ機能を備えた無料の家計簿アプリですが、いくつかの違いがあります。
| 項目 | マネーフォワード ME | マネーフォワード for ひまわり生命 |
|---|---|---|
| 利用料 | 無料(有料プランあり) | 完全無料 |
| 連携口座数(無料プラン) | 最大4件 | 最大10件 |
| 広告表示 | あり | なし |
| デザイン | 機能が豊富でやや複雑 | シンプルで見やすい |
どちらも優れたアプリですが、「とにかくシンプルに、無料で使いたい」方にはひまわり生命版が向いていると感じました。
一方で、有料プランの高度な分析機能やより多くの連携先が必要な方は、「マネーフォワード ME」の有料版も選択肢になります。
私の使い方:毎日じゃなくてOK!週1回でも十分
「毎日つけなきゃ」「続けられるかな」と不安に思う方も多いですが、私は週に1回だけチェックするスタイルです。
私のルーティン:
- 土曜の夜に1週間の支出をチェック
- 支出の分類がズレていたら修正
- 今週の反省と翌週の予算を確認
これだけでも十分、無駄遣いを抑える効果があります。
なぜなら「見える化」することで、「何にどれくらい使っているのか」を意識できるからです。
三日坊主にならない!家計簿アプリを続ける3つのコツ
1. 完璧を目指さない
最初から全ての支出を細かく記録しようとすると疲れて続きません。
ざっくり「食費・日用品・こども関連」くらいで十分。
抜けがあってもOK、「気づいたときに見直す」くらいの気楽さが大事です。
2. 自動記録に頼る
「手入力」はやっぱり手間です。
アプリの強みである自動連携をフル活用すれば、ほぼ“放っておくだけ”で記録が完成します。
手書きの家計簿とは比べものにならない時短効果!
3. グラフやレポートを楽しむ
グラフで「今月は○%節約できた」とか、「教育費が増えてる」など視覚的に変化がわかると楽しいです。
ご褒美的に「節約できた週はカフェOK!」みたいな目標を立てるのも◎。
家計の見直しってどう進めればいい?
アプリで収支が見えるようになったら、次は家計の見直し。
私は以下の3ステップで進めました。
ステップ1:固定費をチェック
まずは「毎月必ず出ていくお金」=固定費を見直しました。
- 通信費(格安SIMへ変更)
- サブスク(使っていないものを解約)
- 保険(内容を見直して月額ダウン)
ステップ2:月の予算をざっくり設定
「食費3万円・日用品1万円・教育費1万円」など、ざっくりでOK。
月の収入と相談して、予算を超えない意識をもつだけでも違います。
ステップ3:変動費の使い道を意識
レジャーや外食などの変動費は「月○回まで」などルールを決めました。
子どもと相談して、家族で使い方を決めるのも楽しいですよ!
まとめ:家計簿アプリで無理なく続ける仕組みを
忙しいママでも、アプリの力を借りれば家計管理はグンと楽になります。
特に「マネーフォワード for ひまわり生命」は、無料かつ自動化できる点が大きな魅力。
- 自分のペースで続けられる
- 家計の見える化ができる
- 家族とのお金の会話も増える
最初の一歩は、「インストールして連携するだけ」。
難しく考えず、気軽に始めてみてくださいね。
次回予告:子どもにどう教える?わが家のおこづかいルール
次回は、小学生の子どもたちにどうやって「お金の使い方」を伝えているかをご紹介します。
わが家のおこづかいルールや、ちょっとした金銭教育の工夫もシェア予定です。
「おこづかいって何歳から?」「金額はどう決める?」など、気になる疑問にも答えていきますので、ぜひ読みに来てくださいね!


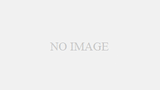
コメント